実家の相続はどうしたらいい?6つの選択肢や手続き完了までの流れを解説
2025.01.27

実家を相続するときの選択肢は「実家に住む・賃貸として貸し出す・更地にして土地活用する・売却する・限定承認する・相続放棄する」の6つあります。
相続手続きの流れは、遺言書の有無の確認から相続税の申告と納付まであり、各手続きで期間があるため注意が必要です。
この記事では、実家を相続するときの6つの選択肢や手続き完了までの流れ、相続前後にかかる税金や相続時の注意点を解説します!
目次
実家を相続するときの選択肢6つ

実家を相続するときの選択肢は以下の6つがあります。
- 1.実家に住む
- 2.賃貸として貸し出す
- 3.更地にして土地活用する
- 4.売却する
- 5.限定承認する
- 6.相続放棄する
それぞれの選択肢を見ていきましょう。
1.実家に住む
まずは自分や兄弟、親戚が住むのを検討すると良いでしょう。ただし、実家に誰かが住んだ場合は毎年固定資産税がかかり、老朽化が進んでいる場合には修繕費なども発生します。
親族が住むのが最も手間のかからない方法ですが、相続人が複数いる場合には、相続する財産の分配方法に注意しなければなりません。
2.賃貸として貸し出す
立地条件の良い場所に実家があるなら、賃貸として貸し出す方法もあります。しかし、建物が劣化している場合や設備が古い場合には、リフォームする必要が出てきます。
そのため改修費用がどれくらいかかるかも検討しておきましょう。また賃貸として貸し出す場合、借り手が見つかれば一定の家賃収入が見込めるのがメリットです。
3.更地にして土地活用する
実家を更地にして土地を活用する方法があります。更地にしたあとは、駐車場やアパート、小型テナントビルなどにして利用する方法です。解体や建設に費用がかかりますが、一定の収入を見込めます。
土地活用の条件は以下の通りです。
- ・駅が近い
- ・近くに大規模な工場や企業、大学、商業施設がある
- ・すでにアパートやマンションが多い
これらの条件に当てはまる場合は、土地活用に適しているといえます。また、小型テナントビルにして利用すると、以下のようなメリットがあります。
- ・比較的立地の影響を受けにくい
- ・アパート経営より収益が大きくなる可能性がある
- ・トラブル発生のリスクが低い
- ・初期費用やランニングコストを抑えられる
アパート経営は立地の影響を受けやすく、入居率に関わってきますが、小型テナントビルの場合、駅近でなくても入居者を募集しやすく立地の影響を受けにくい特徴があります。
4.売却する
実家に誰も住む人がいない・立地条件が良くない・管理が面倒・土地活用も検討していないなどの場合には、売却するのもひとつの方法です。
売却の際は、不動産会社に相談すると良いでしょう。どの不動産会社にしようか悩んでいる際には、不動産一括査定サイトを利用する方法もあります。
ただし、選択に迷ったり電話対応が大変になったりするデメリットもあるので、注意が必要です。
5.限定承認する
実家を相続する際にマイナスの財産があるかもしれない場合、限定承認する方法もあります。
限定承認とは被相続人の借金などマイナスの財産があった場合、プラスの財産の範囲内で相続人が責任を負うというものです。
プラスの財産は現金や不動産などを指し、マイナスの財産はローンなどの借金を指します。
プラスの財産の方がマイナスの財産を上回る場合、手元に遺産が残りますが、マイナスの財産が下回る場合は、プラスの財産の範囲内で返済するため、プラスマイナス0になるわけです。
ただし、限定承認は相続人が複数人いる場合、必ず全員で行わなければなりません。また、手続きの期限も3ヶ月以内と短い期間で行う必要があります。
6.相続放棄する
解体費用や維持費用が出せないという場合は、相続放棄もできます。しかし、実家のみならずすべての財産を放棄することになるため、注意が必要です。
とはいえマイナスの財産の方が上回る場合は相続放棄の方が良いケースもあります。相続放棄しても、受取人になっている生命保険金は受け取れる仕組みです。
また、相続放棄する場合も手続きの期限は3ヶ月以内となっているため、早めに意思決定する必要があります。
実家を相続して手続き完了までの流れ

実家を相続して手続きが完了するまでの流れや期限は以下のようになっています。
- 1.遺言書の有無の確認
- 2.遺産や債務の確認
- 3.相続放棄する場合の期限の締切(3ヶ月以内)
- 4.準確定申告(4ヶ月以内)
- 5.不動産の名義変更
- 6.相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
それぞれ詳しく解説していきます。
遺言書の有無の確認
まずは亡くなった人の遺言書があるのかを確認します。自筆の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所に「検認」の申立をします。
正式な遺言書であれば、それに従って分割するのが基本です。しかし、遺言書に長男のみに相続させると書いてあった場合、遺産のすべてを長男が相続できます。
ただしその場合でも、他の相続人は遺留分という最低限の権利が認められるため、長男に金銭の支払いを請求できます。
また、エンディングノートの場合、法的な効力は持ちませんが亡くなった人の意志を確かめるのに有用です。
遺産や債務の確認
次に遺産や債務を確認します。亡くなった人が生前に契約していた銀行や証券会社、保険会社などの金融機関に連絡し、状況を細かく把握しましょう。その際に、借金があるかどうかも確認が必要です。
内密にしていた借金がある場合、調べるのに時間がかかる可能性もあるため、早めに調べるようにしましょう。
マイナスの財産の方が上回れば、相続した人が返済しなければいけなくなるため、相続放棄も検討することをおすすめします。
相続放棄する場合の期限の締切(3ヶ月以内)
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は相続放棄もできます。
相続放棄する場合の期限は、被相続人が亡くなった日もしくは、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。
先述した通り、限定承認も同様に3ヶ月以内となっています。期限を過ぎてしまうと、亡くなった人が残した借金を相続人がすべて返済しなければならないため、早めの決断が重要です。
相続放棄するか限定承認するかは、弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
準確定申告(4ヶ月以内)
次に準確定申告をする必要があります。準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を確定申告することです。
準確定申告は、被相続人がアパート経営や個人事業などを行っていたり、年金収入を得たりしていて、毎年所得税の確定申告をしていた場合に行う必要があります。期限は被相続人が亡くなった日から4ヶ月以内です。
ただし、年金収入が400万円以下であり、所得が20万円以内の場合は、確定申告は不要となります。
不動産の名義変更
実家を相続をする場合、不動産の名義を変更する必要があります。
相続後の不動産名義変更を「相続登記」といい、2024年4月からは義務化されるため、必ず名義変更をしなければなりません。
期限は3年以内で、登記申請しないと10万円以下の過料が発生します。「相続登記」するには次の準備が必要です。
- ・遺産分割協議書
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・印鑑証明
など
遺産分割協議書は銀行や証券会社の口座の引き継ぎにも必要になるので、早めに弁護士や司法書士などの専門家に作成を依頼しましょう。
相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
最後に、相続税の申告と納付をします。期間は被相続人が亡くなった日もしくは、亡くなったことを知った日から10ヶ月以内です。
ただし、相続税がかからない場合の申告義務はありません。相続税の基礎控除の範囲内などがこれに当たります。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。相続税に対して不安がある人は、税理士や税務署に相談しましょう。
実家を相続する場合にかかる税金2つ

実家を相続する場合にかかる税金は以下の2つです。
- 1.相続税
- 2.登録免許税
それぞれどれくらいかかるのか、確認していきましょう。
1.相続税
まずは相続税がかかります。相続税は相続する遺産額によって変わってきます。財産が多ければ多いほど、相続税の税率も高くなる仕組みです。
税率は10%~55%と高いため、遺産額の評価額もできるだけ下げるよう努めるのもポイントになります。
以下の表は、遺産額に対しての相続税率を表したものです。
| 遺産額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
表からわかる通り、1,000万円以下は控除額がありません。遺産額を計算する場合、現金や金融商品などは一般的に時価で計算しますが、実家など土地や建物の場合、建物は固定資産税評価額で算出します。
土地は、相続税路線価による路線価方式か、あるいは固定資産税評価額をもとにした倍率方式で出す、相続税評価額で計算されます。
2.登録免許税
不動産の名義変更である「相続登記」をする場合に国に納める税金として、「登録免許税」がかかります。相続登記の場合、登録免許税は不動産の固定資産税評価の0.4%が課税されます。計算式は以下の通りです。
不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税
不動産の売買や贈与による所有権移転登記の際の登録免許税が税率2%なのに対して、相続登記にかかる登録免許税は約5分の1で税率が低い特徴があります。
実家の相続後にかかる税金

実家の相続後にかかる税金は、相続した実家を売却する場合と、保持する場合で異なります。
ここでは、それぞれのパターンにかかる税金をチェックしていきましょう。
相続した実家を売却する場合
相続した実家を売却する場合にかかる税金は、以下の3つがあります。
- ・譲渡所得税
- ・印紙税
- ・復興特別所得税
譲渡所得税とは、不動産の売却で得た利益に対する所得税と住民税のことです。不動産を購入した金額よりも高く売れた場合に発生します。
印紙税とは、売買の契約書を作成したときにかかる税金です。契約金額が大きいほど印紙税も高くなる特徴があります。
また、復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けた財源を確保するための税金で、所得税に2.1%課税される制度です。令和19年(2037年)まで必要となる税金になります。
相続した実家を保持する場合
相続した実家を保持する場合にかかる税金は、以下の2種類です。
- ・固定資産税
- ・都市計画税
固定資産税とは、固定資産を所有している場合にかかる地方税のことで、土地や建物などの不動産も固定資産に該当します。
毎年1月1日の時点で不動産を所有している人が自治体に納付する義務があり、建物の築年数やエリアによって税額は変わってきます。
また、都市計画税とは、市街化区域内に該当するエリア内に不動産を所有している人が納める税金のことです。
都市計画税は公園の建設や道路の整備、上下水道の整備などの費用として使われます。
実家の相続税を節税する4つの方法
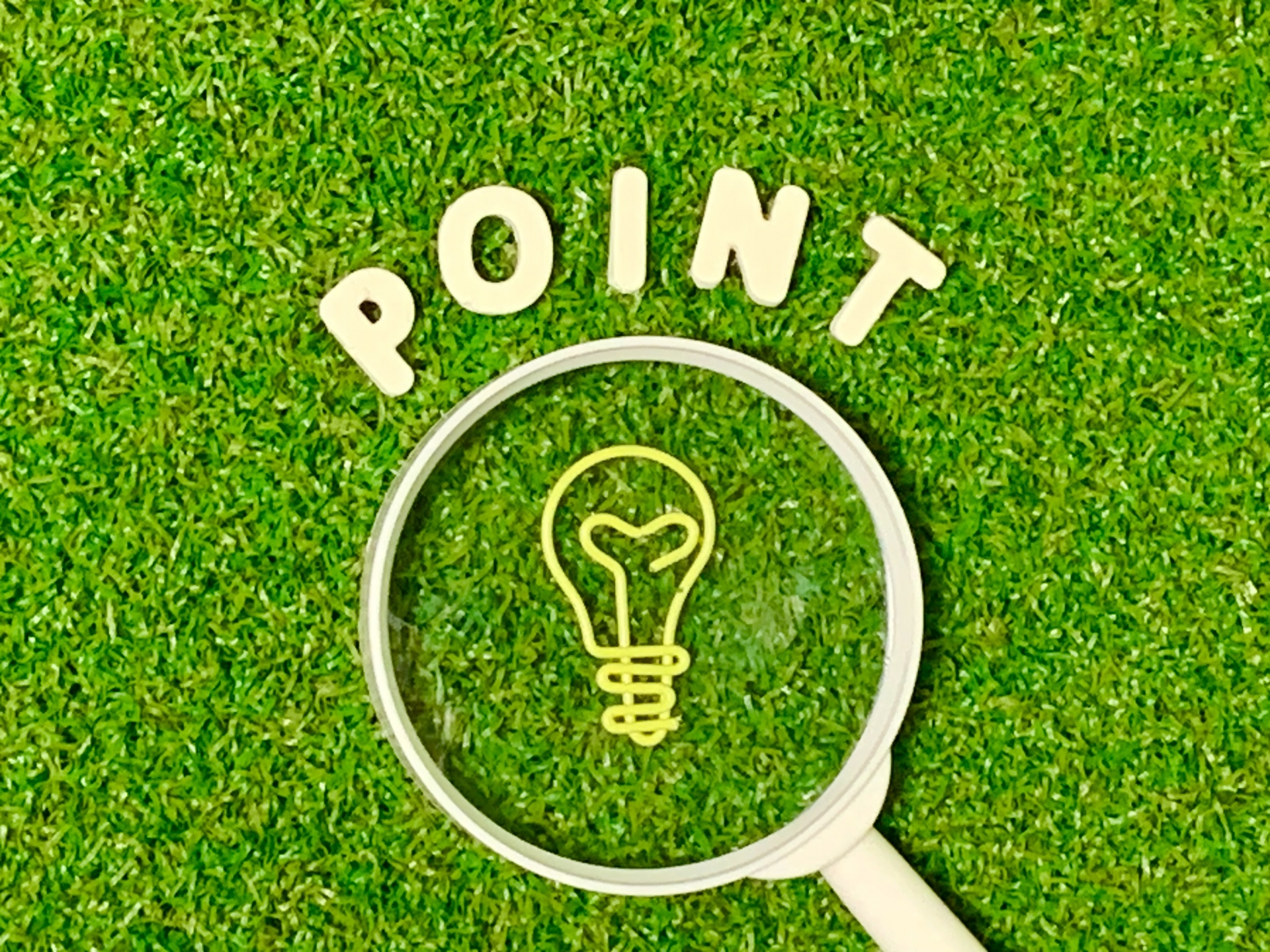
実家の相続税を節税するには、以下の4つの方法があります。
- 1.小規模宅地等の特例
- 2.配偶者の税額軽減
- 3.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 4.相続した実家が空き家の場合の3,000万円特別控除
それぞれ詳しく解説していきます。
1.小規模宅地等の特例
実家を相続する際に、小規模宅地等の特例で節税が可能になります。小規模宅地等の特例とは、特定居住用宅地などに該当する土地は、330㎡まで80%評価額を下げてくれるという制度です。
例えば、土地の評価額が1億円だったとしても、80%評価額を減額してくれるため、2,000万円で評価されます。
ただし、被相続人と同居していた配偶者などが受けられる制度であり、同居していなかった子がこの制度を受けるには、マイホームを所有していないことや、被相続人に配偶者がいない場合などの条件を満たす必要があります。
2.配偶者の税額軽減
相続を受ける人が配偶者の場合は、配偶者の税額軽減が適用されます。配偶者の税額軽減とは、婚姻期間が長短関係なく、相続税の軽減が優遇されるというものです。
具体的には、財産額が1億6,000万円もしくは法定相続分相当額の多い方の金額まで、相続税はかかりません。
例えば相続財産額の評価が100億円で、相続人が配偶者と子1人だった場合、配偶者の法定相続分は2分の1で50億円になります。配偶者の相続財産額が50億円だったとしても、相続税は1円もかからないというわけです。
実家の相続の場合でも、亡くなった父親の配偶者(妻)が健在であれば、この制度を利用してトータルの相続税を大幅に節税できます。
3.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
要件を満たせば相続財産を譲渡した場合の取得費の特例も活用できます。
これは相続税の申告期限から3年以内に実家などの財産を譲渡(売却)した場合に、相続税額の一部が取得費に加算される制度です。
譲渡益は、基本的に売却代金から取得費や譲渡費を引いて算出します。相続した財産の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぐのが原則です。
その際に、この特例を利用すると相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡益を減らせるというわけです。
4.相続した実家が空き家の場合の3,000万円特別控除
相続した実家が空き家で一定の条件を満たしている場合、3,000万円の特別控除が適応になります。
空き家を譲渡(売却)した場合に、譲渡益から3,000万円差し引ける制度です。
例えば空き家を売った譲渡益が3,000万円以内だった場合、所得税は一切かかりません。ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
- ・昭和56年5月31日以前に建築されていること
- ・相続開始直前に他界した人の他に誰も住んでいないこと
- ・令和5年12月31日までに売却されていること
- ・売却額が1億円以下の物件であること
実家を相続するときの注意点3つ

実家を相続するときの注意点は、次の3つです。
- 1.空き家を放置すると罰則がある
- 2.解体すると固定資産税の軽減を受けられない
- 3.共有相続はトラブルにつながる可能性がある
それぞれの注意点を確認していきましょう。
1.空き家を放置すると罰則がある
最もやってはいけないのが空き家を放置することです。空き家の放置は罰則を受ける場合があります。
令和5年12月に空き家等対策の法律が一部改正され、倒壊の恐れがある「特定空き家」に加え、窓や壁が破損している「管理不全空き家」も、自治体からの指導や勧告の対象になっています。
空き家を放置した場合、固定資産税や都市計画税などの軽減措置を受けられなくなるほか、隣人からの損害賠償請求や、行政が強制的に取り壊しを行い、解体費用を請求される場合もあるため注意しましょう。
2.解体すると固定資産税の軽減を受けられない
実家を解体すると固定資産税の軽減を受けられなくなります。住宅用地として使用する場合、土地の固定資産税は最大で6分の1に減税されますが、建物を解体すると住宅用地の軽減措置の対象外になってしまうのです。
建物自体の固定資産税はかからなくなりますが、土地の固定資産税が上がる可能性があるため注意しましょう。
3.共有相続はトラブルにつながる可能性がある
兄弟がいるなど、実家の相続人を複数にする「共有相続」にした場合、トラブルにつながる可能性があるので注意が必要です。
例えば「共有相続」した人全員の同意がなければ、自由に売却や賃貸できないので手間が増えてしまいます。
また、その財産を子どもが相続するとなると、さらにややこしくなるでしょう。これらの理由から、共有相続はできるだけ避けた方が良いといえます。
実家の相続を決めたら、流れに沿って適切な対応をしよう

実家の相続には「住む・賃貸として貸し出す・更地に土地活用する・売却する・限定承認する・相続放棄する」の6つの選択肢があります。
相続を放棄する場合は3ヶ月以内に手続きしなければならないため、早めの決断が必要です。
相続する場合は、かかる税金や節税方法、注意点などを確認しておくと良いでしょう。困った際には、税理士や司法書士、弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

