実家を相続する場合の選択肢とは?必要な手続き・注意点・節税対策を解説
2025.02.20

実家を相続した際には、「維持する」か「手放す」かを最初に検討することが重要です。これにより、その後の手続きや方針が明確になります。
本記事では、具体的な活用方法や必要な手続き、注意すべきリスク、節税のポイントをわかりやすく解説します。計画的な対応でスムーズな相続を目指しましょう。
実家を相続する際の選択肢

実家を相続した後はいくつかの選択肢があります。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあるため、自身の状況や目的に合わせて判断しましょう。
1.自身または親族が居住する
実家を相続する際の選択肢の一つが、自身や親族がそのまま住み続ける方法です。継続して住む選択をすれば、家族の気持ちや思い出を大切にしながら、空き家問題を避けられます。
ただし、住まない場合には固定資産税や管理費用の負担が発生するため、経済的な側面も考慮しなければなりません。
2.賃貸として活用する
実家を賃貸物件として活用すれば、安定した収入を得ることが可能です。不動産を手放さずに資産価値を維持しながら活用できます。ただし、賃貸経営には管理の手間や維持費がかかるため、事前の準備や計画を立てることが重要です。
3.売却する
相続した実家を利用しない場合、売却は有力な選択肢の一つです。売却によって得た資金を別の用途に充てられるだけではなく、固定資産税や維持費などの負担を減らせます。ただし、売却に伴う税金や必要な手続きを事前に確認することが必要です。
4.更地にして活用する
実家を更地にすると、土地の活用方法が広がり、資産価値の向上が期待できます。例えば、駐車場として運用したり、新たな建物を建設したりと、さまざまな用途に活かすことが可能です。ただし、更地化には解体費用がかかる上、固定資産税の負担が増えるケースもあります。
5.相続放棄または限定承認を行う
相続財産よりも債務が多い場合、相続放棄や限定承認も選択肢に入ってきます。相続放棄をすれば、借金などの負担を引き継がずに済みます。一方、限定承認を利用すれば、プラスの財産を残しつつ、債務の負担を最小限に抑えることが可能です。
ただし、どちらの手続きも相続開始から3ヵ月以内に行う必要があり、手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
6.相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した土地を手放したい場合、国庫に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」を活用する方法があります。2023年4月に施行された法律に基づき、一定の条件を満たせば土地を国に帰属させることが可能です。
ただし、建物の取り壊し費用や10年分の管理負担金の納付が必要となるなど、適用条件が厳しいため、慎重に検討することが求められます。
実家を相続するための手続き

実家を相続するためには、遺言書の確認や相続人の特定など、いくつかの重要な手続きが必要です。それぞれのステップを確認していきましょう。
1.遺言書の確認
相続手続きの最初のステップは、遺言書の有無を確認することです。遺言書が存在する場合、その内容が相続の基本方針となり、遺産分割の手続きにも大きく影響します。
ただし、遺言書が法的に有効な形式で作成されているかの確認が重要です。特に自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。また、手元に遺言書が見つからなくても、法務局や公証役場で保管されている可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
2.相続人および相続財産の調査
遺言書の確認が済んだら、次に行うべきは相続人の確定と相続財産の調査です。相続人は戸籍謄本をもとに確認し、特定する必要があります。
また、遺産の内容や価値を明確にすることも重要です。不動産や預貯金、株式だけではなく、負債の有無も調査することで、相続財産全体の状況を把握し、適切な対応を取ることができます。
3.遺産分割協議の実施
相続人と財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。この協議では、誰がどの財産を相続するのかを決めるため、全員の合意が不可欠です。
話し合いの内容は「遺産分割協議書」にまとめ、相続登記や相続税の申告にも必要となるため、正確に記載しなければなりません。協議書には相続人全員の署名・捺印(不動産の相続登記等のため実印)し、法的に有効となることで相続後のトラブルを防ぐ役割も果たします。
4.相続登記の手続き
不動産を相続した場合、所有権を正式に移転するための相続登記が必要です。相続人は法務局に必要書類を提出し、手続きを行うことで、不動産の名義変更ができます。
2024年4月1日から義務化され、相続による取得から3年以内に登記しないと最大10万円の過料が科される可能性があります。登記を怠ると売却や活用が難しくなるため、早めの対応が不可欠です。
5.相続税の申告と納付
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合、相続税の申告が必要です。申告と納付は、相続開始から10ヵ月以内に行わなければなりません。
申告には財産評価の詳細が求められるため、税理士などの専門家のサポートを受けることが一般的です。納税額が大きく一括で支払えない場合は、延納や物納(不動産・株式での納税)も検討しましょう。
相続した不動産を売却するときにかかる税金はいくら?特別控除や注意点をチェック
実家を相続する際の注意点
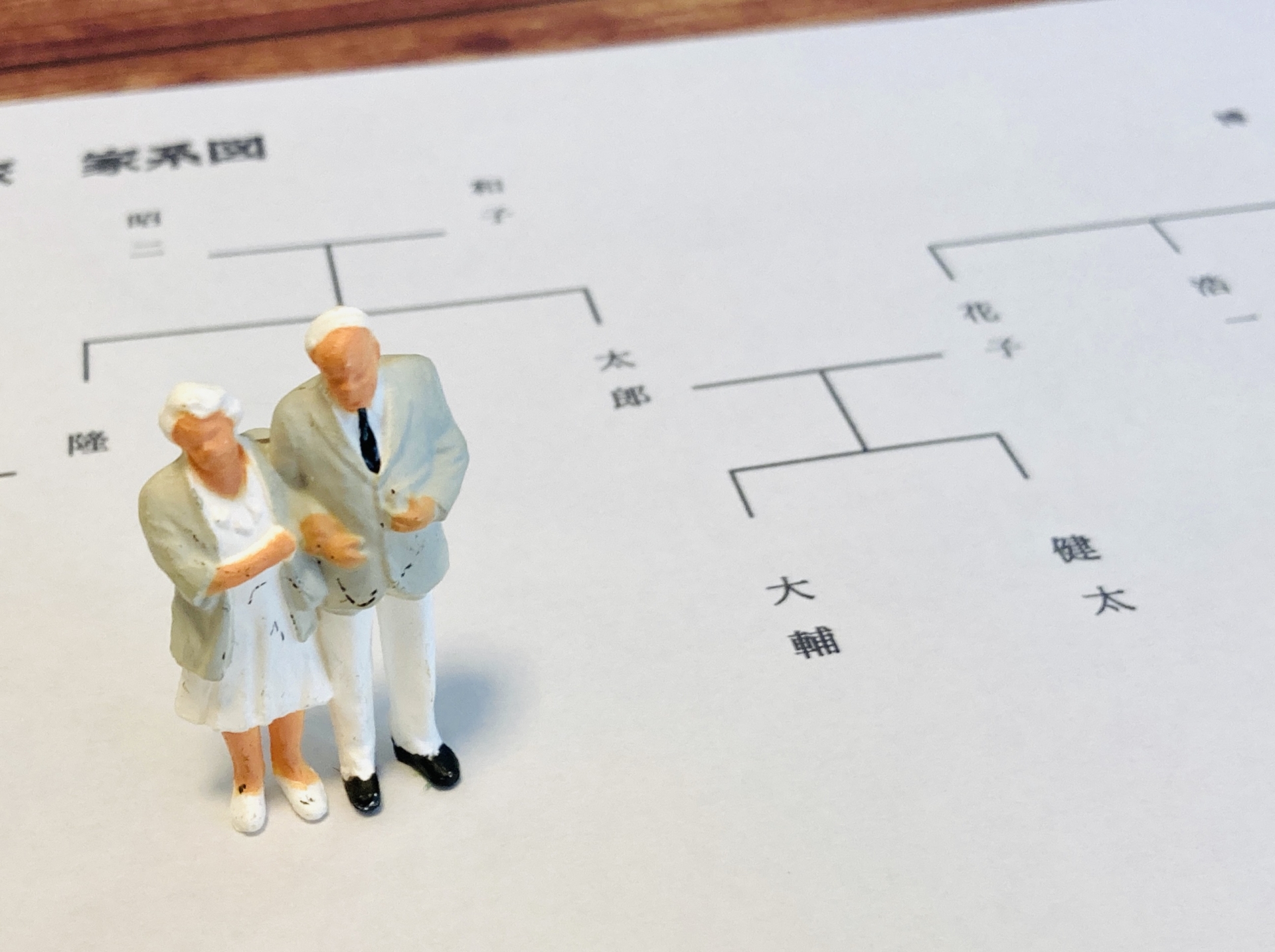
ここでは実家を相続する際の注意点を解説します。
共有名義は運用する中で全員の意見が必要になる
実家を兄弟などと共有名義にすると、売却や賃貸の際に全員の同意が必要となり、意思決定が遅れる可能性があります。もしも意見の対立が生じると、管理や運用にも支障をきたすことがあります。
こうしたリスクを避けるため、できるだけ単独所有にするのが理想的です。共有する場合も、早い段階で運用方針を決めておくことで、トラブルを未然に防げます。
共有持分の不動産は売却できる?4つの方法と費用、トラブル例を解説
空き家にしておく場合は管理が必要になる
相続後に実家が空き家になる場合、適切な管理が必要になります。放置すると老朽化が進み、防犯上のリスクが高まるだけではなく、近隣住民への迷惑につながることも。
また、管理が不十分な空き家は、行政から特定空き家に指定され、改善指導や場合によっては固定資産税の優遇措置が解除される可能性もあります。そのため、定期的な点検や清掃を行う、または専門業者に管理を委託するなどして、適切な管理方法を検討しましょう。
【新改正】管理不全空き家はいつから固定資産税が6倍に?定義や回避方法を解説
更地にした場合は固定資産税が増加するリスクがある
実家を更地にすると、固定資産税が増加する可能性があります。これは、住宅が建っている場合に適用される固定資産税の軽減措置が失われるため。更地にすると税負担が数倍になることもあるため、注意が必要です。
更地化を検討する際は、その後の活用方法を明確にし、固定資産税の負担を計算した上で、十分な準備を行うことが大切になってきます。また、更地にしない場合でも、維持管理のコストがかかるため、どちらの選択肢がより適しているか慎重に検討する必要があります。
相続財産に偏りがあるとトラブルに発展する可能性がある
実家の不動産が相続財産の大半を占める場合、他の相続人との間で不公平感が生じ、トラブルにつながることがあります。特に、実家を長男1人が相続すると、他の相続人が不満を抱きやすいため、慎重な対応が必要です。
このような場合は、遺産分割協議の中で適切な調整を行うことが重要。例えば、現金や他の資産で差額を補填する方法や、実家を単独で相続する人が代償金を支払うといった対応が考えられます。また、後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書をしっかり作成し、合意内容を明確にしておくことが大切です。
実家の相続税の節税対策4つ

ここでは実家の相続税を抑えるための対策を解説します。
1.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たす土地に対して相続税評価額を最大80%減額できる制度です。これにより、相続税の大幅な軽減が可能となります。適用を受けるためには、被相続人が住んでいた土地や事業用の土地であり、相続人が引き続き利用するなどの要件を満たす必要があります。
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
小規模宅地等の特例とは?要件や計算法、必要書類をわかりやすく解説
2.配偶者の税額軽減措置
配偶者が相続する場合、相続税の税額軽減措置を利用することで、一定額までの相続税が免除される可能性があります。この制度は、配偶者の生活資金を確保し、経済的負担がかからないようにすることを目的としています。
ただし、適用を受けるには相続税の申告が必要です。
3.相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を受けられます。この制度を利用すると、売却時の所得税負担を大幅に軽減することが可能です。
適用には、被相続人が住んでいた家屋であること、耐震基準を満たしていることなどの条件をクリアする必要があります。
4.取得費加算の特例
相続した財産を売却する際に取得費加算の特例を利用すると、相続時に支払った相続税を取得費に加算でき、売却時の譲渡所得税を軽減できます。
ただし、この特例を適用するには、相続税の申告を行っていることが条件となるため、事前の確認が欠かせません。
実家を相続する際は早めの計画と相談を
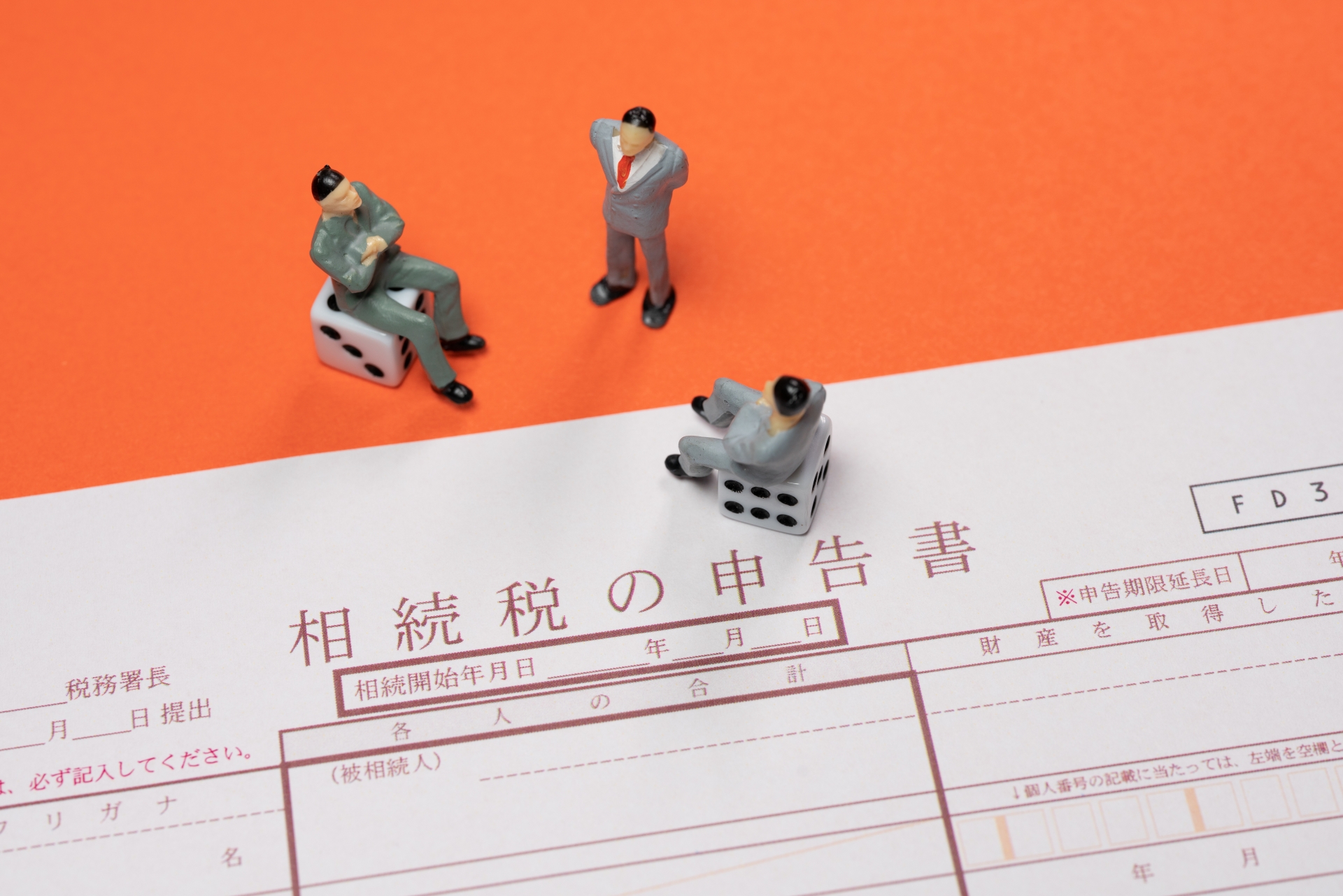
実家の相続では、選択肢の検討や手続きの準備、リスク対策が欠かせません。
スムーズに進めるためには、事前の計画と的確な対応が重要です。全体を見通し、慎重に判断することで、トラブルを未然に防げます。複雑な手続きを確実に進めるためには専門家のサポートも検討してみてください。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

