遺産相続した土地の相続登記の期限はいつまで?手続き一覧・流れ・放置するリスク
2025.03.20

土地を相続したら、相続登記を3年以内に申請することが義務化されています。取得を知った日、または遺産分割成立日から3年以内に手続きを行わなければ、過料の対象となる可能性も。
期限を守らないと売却や活用が制限されるため早めの対応が重要です。この記事では、土地の相続手続き一覧や流れ、放置するリスクなどについて詳しく解説します。
目次
土地の遺産相続で期限のある手続き一覧

土地を相続した際には、期限が定められた手続きがいくつかあります。特に相続放棄や相続税の申告、相続登記は、期限を過ぎると法的な不利益や罰則が発生する可能性があるため注意が必要です。
まずは、スムーズに相続手続きを進めるためにも、それぞれの手続きの期限と必要な準備を見てみましょう。
3ヶ月以内|相続放棄・限定承認
相続財産に借金が多い場合、相続放棄や限定承認を選択できますが、その手続きは相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に完了させなければなりません。期限を過ぎると、相続を受け入れたとみなされ、財産と負債の両方を引き継ぐことになります。
相続放棄は、被相続人の財産も負債も受け取らない方法であり、一方の限定承認は、相続した財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。どちらを選択するかは、財産の調査が不可欠ですが、調査に時間がかかる場合は家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請することも可能です。
ただし、この延長が必ず認められるわけではないため、早めに相続財産を確認し、判断を下すことが重要です。
10ヶ月以内|相続税の申告・納税
相続税の申告・納税は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課され、最悪の場合、財産の差し押さえに至るケースもあります。
相続税の申告が必要になるのは、相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。
納税は原則として現金一括払いですが、延納や物納といった方法も選択できるため、早めに相続財産の評価と資金計画を立てることが重要です。
3年以内|相続登記(2024年4月1日から義務化)
2024年4月1日から相続登記が義務化され、所有権の取得を知った日から3年以内に手続きを完了しなければなりません。期限を過ぎた場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は、2024年4月1日以降に発生したものだけではなく、過去の相続不動産についても時効とはならず、適用されます。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きであり、これを行わなければ、不動産の売却や担保設定ができず、相続人同士のトラブルの原因になりかねません。また、相続登記を放置すると、時間の経過とともに相続人の数が増え、手続きがさらに複雑化する恐れがあります。
登記の申請には、遺産分割協議書や戸籍謄本、固定資産評価証明書などの書類が必要となるため、早めに準備を進めましょう。
東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~」
土地を遺産相続する際の流れ
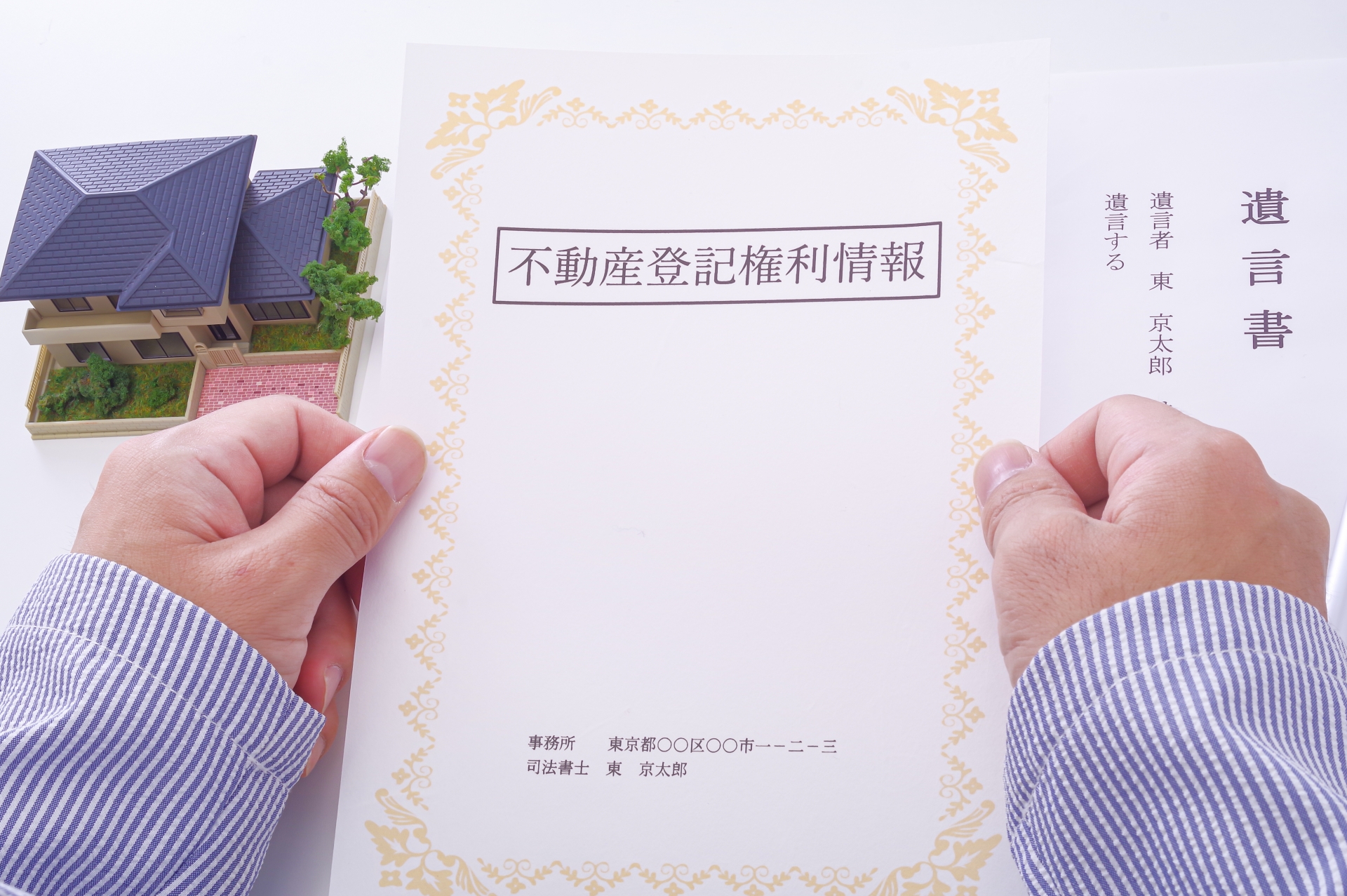
土地を相続する際には、複数の手続きを順番に進める必要があります。ここでは、土地の遺産相続の流れを詳しく解説します。
1.相続の開始
相続は、被相続人の死亡と同時に自動的に開始されます。遺族は まず死亡届を提出し、葬儀の手配を行うとともに、相続に関する手続きを進める必要があります。相続には期限がある手続きが多いため、どの手続きを優先すべきかを把握し、計画的に進めることが重要です。
2.相続人と相続財産の調査
相続の第一歩は、相続人の確定と相続財産の把握から始まります。相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで遡って取得し、法定相続人を特定します。
また、不動産、預金、借金などの財産を一覧にして、相続財産の全体像を把握することが必要です。財産調査を怠ると、後から債務が発覚するなどのトラブルが生じる可能性があるため、できるだけ早い段階で正確な情報を収集しましょう。
3.遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を文書化することが重要です。遺言がある場合はその内容に従って相続手続きを進めますが、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
協議がまとまれば、合意内容を遺産分割協議書に記載し、各相続人の署名・押印を行います。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判へと発展する可能性があるため、早めに合意形成を進めることが重要です。
4.相続登記の手続き
相続した不動産を正式に相続人の名義に変更するため、相続登記を行います。
相続登記を進めるには、被相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などの必要書類を準備し、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。法務局の審査を経て、問題がなければ登記が完了し、不動産の名義変更が正式に行われます。
登記完了後は、登記簿謄本を取得し、正しく手続きが行われたかを確認することが重要です。
5.相続税申告と納税
相続税の申告は、財産の評価と分割内容が確定した後に行います。まず、すべての財産を一覧にした財産目録を作成し、不動産、預貯金、株式などの評価額を算出します。次に、遺産分割協議の結果を反映し、各相続人が取得する財産を確定。
その後、必要に応じて添付書類を準備し、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税申告書を提出します。
遺産相続手続きをせずに土地を放置するデメリットとは

土地を相続した後、手続きをせずに放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。将来的なトラブルを避けるためにも、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、相続した土地を放置することで生じる具体的なデメリットについて解説します。
共有名義のままだと売却や活用ができないなどのリスクがある
不動産を共有名義のままにすると、自由に売却や活用することが難しくなります。共有不動産の処分には、すべての共有者の同意が必要となるため、相続人が増えると意思決定が複雑になり、話し合いが難航することもあります。
また、共有者の一人が亡くなると、その持分が新たな相続人へ引き継がれ、権利関係がさらに複雑化することも。こうした事態を避けるために、早めに単独名義に変更するか、共有持分を売却するなどの対策を検討することが重要です。
固定資産税や維持費が負担になる
不動産を所有している限り、活用の有無にかかわらず固定資産税や維持費が発生します。特に、空き家のまま放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税が大幅に増額されるリスクも。
また、建物が老朽化すれば修繕費や管理費もかかるため、経済的な負担が増える可能性が高くなります。こうした負担を回避するためにも、売却や賃貸などの活用方法を早めに検討し、適切な管理を行うことが必要です。
土地の遺産相続の他に期限がある手続き

相続では不動産に関する手続き以外にも、期限を守らなければならない手続きが多数あります。それらの手続きも期限を過ぎると、権利が失われたり罰則を受けたりする可能性があるため、早めに対応することが重要です。
遺産相続に関する主な手続きの期限一覧は以下のとおり。
| 期限 | 手続き内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請 | 市区町村役場へ届け出を行わないと、火葬許可証が発行されず葬儀を進められない |
| 14日以内 | 年金の受給停止・健康保険の資格喪失手続き | 申請が遅れると、年金の過払い分を返還しなければならない可能性がある |
| 4ヶ月以内 | 被相続人の準確定申告 | 被相続人が事業所得や不動産所得を得ていた場合、期限内に申告を行わないと延滞税が発生する |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 遺言に法律の定めを越えた不公平があった場合、1年以内に請求しないと権利が消滅する |
| 2年以内 | 埋葬料・葬祭費の請求 | 被相続人が健康保険加入者だった場合、葬祭費の補助を受けられる |
| 3年以内 | 生命保険金の請求 | 保険金の請求には3年の時効がある。期限を過ぎると、保険金を受け取る権利が失われる可能性がある |
| 5年10ヶ月以内 | 相続税の還付請求 | 相続税を払いすぎた場合、期限内に請求しないと還付されない |
土地の遺産相続は期限内に行おう

土地の遺産相続は、期限内に適切な手続きを行うことが重要です。相続登記は3年以内に申請しないと過料の対象となる可能性があり、放置すると権利関係が複雑化、売却や活用が困難になります。
また、相続税の申告や他の手続きにも期限があるため、計画的に進めることが大切です。スムーズに手続きを終えるためにも必要な期限を把握し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

