遺言執行者とは?役割・義務からできることまで、わかりやすく解説
2024.12.13

遺言執行者とは、遺言者の代理として遺言内容を実行する人のことです。必ず選任が必要なわけではありませんが、遺言執行者でなければ実行できない相続内容がある場合は誰かがその役割を担わなければなりません。
とはいえ、遺言執行者は具体的に何をするのか、そもそもどのように選ばれるのかなど疑問もあることでしょう。
そこで本記事では、遺言執行者の役割や義務から選任方法まで解説します。
目次
遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言者の代理として遺言内容を執行する人を指し、相続手続きを行うのが役割です。遺言執行者は遺言書で指定されたり、遺言書に記載がなかった場合は遺言者の死後に選定されたりする場合があります。
また、指定された人は遺言執行者に就職するかを選択でき、必ず引き受けなければならないわけではありません。
役割
遺言執行者の役割は相続手続きの管理・監督をするだけでなく、行為そのものを実施することです。
民法第1012条1項では以下のように定義されています。
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。引用:民法第1012条1項目
遺言書が開封されるのは遺言者が亡くなった後であり、当然ながら遺言者が自ら遺言内容の実行はできません。
そこで遺言執行者が代理として、遺言通りに実現するよう力を尽くすのです。
2つの義務
遺言執行者が行う具体的な内容は遺言によって異なりますが、民法によって定められた共通する2つの義務があります。
1つ目は通知義務です。相続人全員に対し、遺言書の写しと遺言執行者の就職通知書を送付し、遺言執行者に就任した旨を告知します。
(遺言執行者の任務の開始)
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。引用:民法第1007条2項
2つ目は財産目録の作成と交付です。遺言執行者は遺言者の不動産権利証や預金通帳などの所在を確認し、保管する管理業務と同時進行で相続財産調査を行います。また、戸籍謄本を調べて遺言者の相続人を確定しなければなりません。その後、作成した相続財産目録を相続人に対し交付します。
(相続財産の目録の作成)
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。引用:民法第1011条1項
遺言執行者は上記の義務と全ての遺言内容を実行したのち、相続人へ完了を報告します。
遺言執行者が管理・監督・行為できること

前述の通り、遺言執行者は相続の管理・監督だけでなく行為まで行えます。例えば、不動産売却やそのお金を相続人に分配すること、預貯金の解約・払い戻しなどです。
2019年に民法が改正されたことにより、遺言執行者の権限が明確化しました。そのため、相続人と利益が相反していた場合でも遺言内容に従って実行できます。
具体的に遺言執行人ができることは以下の内容です。
- ・相続人調査
- ・相続財産調査・管理
- ・不動産の登記申請手続き
- ・自動車の名義変更
- ・保険金受取人の変更
- ・預貯金の払い戻し・分配
- ・寄付など
なお、遺言執行者を通さずに相続人が無断で財産を処分した場合は、遺言執行の妨害とみなされ無効となります。
遺言執行者の選任は必ずするもの?

遺言執行者の選任は必ずするわけではありません。
ただし、遺言執行者のみに権限が付与される手続きがあります。例えば以下のようなケースです。
- ・非嫡出子の認知
- ・相続廃除
これらを遺言で行うのは遺言執行者にしかできないため、遺言書に記載のあった場合は遺言執行者を選任する必要があります。
一方で、遺言執行者の選任が必須ではないものの、相続人だけではスムーズに手続きが行えない以下のような場合は選任しておくのがおすすめです。
- ・遺言書の内容に納得していない人がいる
- ・多忙で相続手続きに協力できない人がいる
- ・認知症の人がいる
遺言執行者を選任する2つの方法
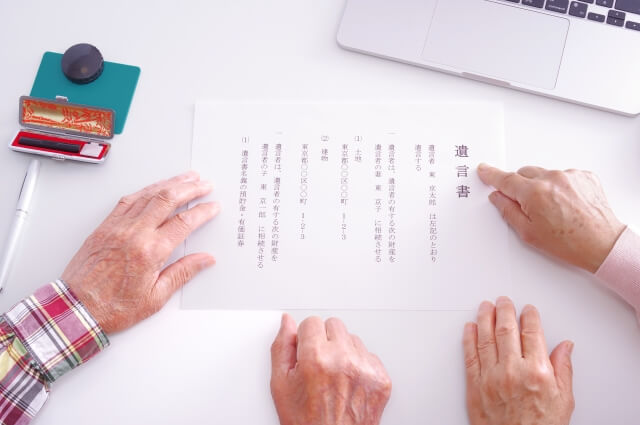
遺言執行者の選任には、遺言者が遺言にて指定するか、遺言者が亡くなったのちに相続人が家庭裁判所へ申し立てをするかの2通りがあります。
なお、家庭裁判所への申し立ては、遺言にて遺言執行者が指定されていない場合や遺言執行者が亡くなった場合に行なわれる選任方法です。
1.遺言で遺言者本人が指定する
遺言執行者を誰にするかは、遺言にて遺言者本人が指定できます。その際に遺言書に記載すべき内容は以下の通りです。
<記載事項>
- ・指定したい遺言執行者の住所・氏名
- ・遺言執行者に選任する意思表明
以下は遺言執行者を指定する際の記載例です。
<遺言執行者を住栄太郎に指定する場合の記載例>
| 第◯条 遺言者は、この遺言の実現のために、遺言執行者として次の者を指定する。 なお、遺言執行者は必要と認めたときには第三者にその任務を行わせることができる。 ◯◯県◯◯市◯◯町△丁目△番△号 |
なお、遺言者本人の存命中は、本人の意思で遺言執行者を変更できます。
具体的な方法としては、新しい遺言書を作成して新たに遺言執行者を指名するか、遺言書の全部または一部の撤回が可能です。
2.遺言者の死後、家庭裁判所へ申し立てをする
遺言で遺言執行者が指定されていなかったり、遺言執行者が亡くなったりした場合は、遺言者の死後でも家庭裁判所へ申し立てをすることで遺言執行者を選任できます。
| 申立人 | 相続人 利害関係人(遺言者の相続債権者、遺贈を受けた人など) |
| 申立先 | 遺言者が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 遺言書1通につき収入印紙800円 連絡用の郵便切手 |
| 必要書類 | 家事審判申立書 標準的な申立添付書類
|
遺言執行者が指定されていなかった場合は、相続人や遺贈を受けた人が全員で遺言内容の実現に努めるのが原則です。
そのうえで、前述したように遺言執行者しかできない手続きがある場合や、遺言内容に不満を持つ人、忙しく時間が取れない人などがいる場合に遺言執行者の申し立てを行うとよいでしょう。
遺言執行者への選任が相応しい人

遺言執行者になるにあたって特別な資格は不要です。また、個人・法人を問わず就任でき、相続人と同一人物だとしても違法にはなりません。
ただし、相続人が遺言執行者を引き受けると、遺言内容が希望に反した場合に執行に対し精神的負担が大きくなります。そのため、遺言執行者は遺言内容に対して利害のない第三者に依頼するのが望ましいでしょう。また、法的な手続きを取ることも多いことから、以下のような人物が適当です。
- ・弁護士
- ・行政書士
- ・税理士
- ・司法書士
- ・信託銀行
遺言執行者に就任不可な人

遺言執行者に就任不可とされるのは、相続開始の時点における未成年者と破産者に該当する人です。
ただし、未成年でも既婚者であれば成人とみなされるため、遺言執行者に就任できます。
また、破産者の場合は裁判所から免責許可の決定を受けることで、遺言執行者に就任可能です。
遺言執行者に支払う報酬相場

前述の「遺言執行者への選任が相応しい人」の記載にあるように、士業や信託銀行の人に依頼した場合、遺産総額の1〜3%が報酬の相場です。
ただし、遺言執行者への報酬に法的な基準はなく人によって異なります。そのため、契約する前に必ず確認しておきましょう。なお、遺言者が生前に依頼しすでに契約を結んでいる場合はその契約書に従う必要があります。
また、遺言執行者への報酬は相続人が遺産から支払うのが一般的です。
遺言執行者の選任に迷ったら専門家へ相談

遺言執行者とは、遺言者の意思を継いで遺言内容の実現を図る人のことで、成人していて破産者でなければ誰でもその役目を担えます。ただし、法的な手続きが多く、相続人が就任した場合は精神的負担になりやすいのが実情です。
相続人全員が納得のうえで遺言内容を実現できるよう、選任に迷った場合は専門家への相談を検討してみましょう。
監修
佐々木総合法律事務所/弁護士
佐々木 秀一
弁護士
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。

